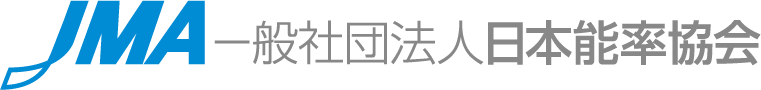顧客が欲しているのは「ドリルの穴」 2022/01/12 KAIKA Tweet
一般社団法人日本能率協会 KAIKA研究所
近田高志
「昨年、1/4インチ口径のドリルが100万個売れたのは、人びとが1/4インチのドリルを欲しかったからではない。1/4インチの穴が欲しかったのである」
 ご存知の方も多いと思いますが、これは、マーケティングの大家であるセオドア・レビット博士が、著書『マーケティング発想法』(1971年/原著は1968年出版)の中で紹介した有名な話です。
ご存知の方も多いと思いますが、これは、マーケティングの大家であるセオドア・レビット博士が、著書『マーケティング発想法』(1971年/原著は1968年出版)の中で紹介した有名な話です。
レビット博士は、企業が商品やサービスを販売するときに、その商品・サービスの機能のみに着眼し、狭く定義してしまうことによって、競合や環境変化に対応できなくなるという「マーケティング近視眼」を提唱したことでも有名です。
これほど良い得て妙な格言が今日も語り継がれているということは、顧客が求めている価値を明らかにし、それに応えた商品やサービスを開発していくことが、いかに難しいことであるかの裏返しではないでしょうか。
その証拠に、レビット博士以降においても、『イノベーションのジレンマ』で有名なハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授が「ジョブ理論」(顧客は達成したい「ジョブ」=“jobs to be done”を片付けるために、商品やサービスを「雇う」という考え方)を提唱したり、あるいは、昨今、多くの企業が取り組んでいるDX(デジタルトランスフォーメーション)において、顧客経験価値(UX:User ExperienceあるいはCX:Customer Experience)が重要であるという指摘がされたりするなど、同様の考え方が発信され続けています。
このように、顧客視点に立って考えることの重要性は誰もが分かっていることながら、実際に視点を変えるということは、案外に難しいことなのです。
これに関して、日本と欧州でコンサルタントとして活躍された故・今北純一氏の話が思い出されます。筆者は、日本能率協会が主催したグローバルリーダー育成プログラムの講師として、今北氏をお招きしたことがありますが、その講演のなかで、視点を変えることの難しさを次のように語られました。
料理屋のカウンターで食事をされたことがあるかと思います。板前さんは、座っているお客の様子を見ながら、料理の内容や提供するタイミングを見計らい、最高のおもてなしをします。その板前さんが板場からどのような景色を見ているのか。想像できるかもしれませんが、実際には、板場に立ってみないと分からないものです。(※筆者が耳にした内容の記憶をもとに再現したものです)
 商品やサービスの開発の際に、民俗学におけるフィールドワークの手法を取り入れて、徹底的に顧客の行動を観察する「ビジネス・エスノグラフィ」や、あるいは、地域や生活空間を舞台にして、想定顧客を交えたワークショップ形式で、商品やサービスのニーズを聞き出し、プロトタイプを作成して、フィードバックを受けながら、改良していくという「リビング・ラボ」の手法などは、顧客の視点をよりリアルに把握するための工夫と言えるでしょう。
商品やサービスの開発の際に、民俗学におけるフィールドワークの手法を取り入れて、徹底的に顧客の行動を観察する「ビジネス・エスノグラフィ」や、あるいは、地域や生活空間を舞台にして、想定顧客を交えたワークショップ形式で、商品やサービスのニーズを聞き出し、プロトタイプを作成して、フィードバックを受けながら、改良していくという「リビング・ラボ」の手法などは、顧客の視点をよりリアルに把握するための工夫と言えるでしょう。
市場が成熟化し、一方で、顧客のニーズが多様化しているという時代にあって、顧客が真に求めている価値とは何か。あらためて、マーケティングの原点に立ち返って考える必要があるのではないでしょうか。