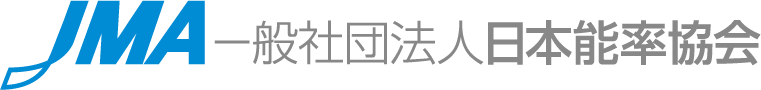民主化と開発の裏で―ミャンマー・レポート 2013/11/25 コラム Tweet
日本能率協会 JMAマネジメント研究所 主管
肥本英輔
◆ 素顔1.Last buddhist-仏とともに生きる人々
11月中旬の土曜日。ミャンマーの最大都市ヤンゴン市内から寝釈迦仏のあるバゴーまでバスで90分。乾季に入ってジリジリと焼ける日差しの中を、単調な農村の風景がゆっくりと流れていく。業務視察を終えて、うとうとする視察団メンバー。ふと、ミャンマー独特の風変わりな音楽が遠くから聞こえてくる。すると、寄進の品や本物の紙幣を貼り付けた派手な飾り物を載せたトラックやオート三輪が、右翼の街宣車のような大音響とともに、何台も猛スピードで車窓を通り過ぎていく。あわてて目を覚ます。
 現地のガイドさんに聞くと、町の消防団の一行ではないかという。明日が11月の満月のお祭りの日で、その日は、ミャンマーの仏教徒にとっては、お寺への寄進ができるありがたい日なのだという。ガイドさんも明日のお祭りをとても楽しみにしていると屈託なく笑った。どうやら先の一団は、寄進先のお寺に向かいながら、通りすがりの人々に大音響で寄付を呼びかけているらしい。沿道の町や村でも、至る所で国道に乗り込んで踊ったり、牛舞(?)を演じながら寄付を募っている。まさにお祭り騒ぎだ。
現地のガイドさんに聞くと、町の消防団の一行ではないかという。明日が11月の満月のお祭りの日で、その日は、ミャンマーの仏教徒にとっては、お寺への寄進ができるありがたい日なのだという。ガイドさんも明日のお祭りをとても楽しみにしていると屈託なく笑った。どうやら先の一団は、寄進先のお寺に向かいながら、通りすがりの人々に大音響で寄付を呼びかけているらしい。沿道の町や村でも、至る所で国道に乗り込んで踊ったり、牛舞(?)を演じながら寄付を募っている。まさにお祭り騒ぎだ。
どんなに貧しくともミャンマーの仏教徒は喜んで寄進する。
ミャンマーといえば、日本人にとっては「ビルマの竪琴」。市川昆監督の映画が有名だが、もともとはビルマ戦線にいた若い日本兵が戦争の悲惨さ、人生の虚しさに目覚めて、現地のお坊さんになってしまうという感傷的な児童文学だ。ビルマ風の竪琴を奏でながら、帰国する僚兵に別れを告げるシーンが印象的だ。
しかし、なぜかこれがミャンマー人の不興を買い、上映はおろか、撮影許可すら下りなかった。実は、ミャンマーの僧侶は音楽を演奏することを戒律で固く禁じられている。歌うことすら許されない。ついでにいえば、オウムを肩に乗せることもはばかられる。それほど戒律は厳しい。現地では当たり前のことだが、日本の進歩派文化人たちにはこれが理解できなかった。日本人のぽっと出の坊主が戒律を破って楽器を演奏するといった軽薄な商業映画など、言語道断の極みなのだ。
 ミャンマーは最近、アジアのLast frontierといわれることが多いが、それは経済の話。現在でも男の子が生まれると、お坊さまにすることが親の最大の喜びだという。ミャンマーの仏教徒は少なくとも一生に1度は必ず出家する。企業経営者ですら剃髪して修行する。身につけるのはロンジー(巻きスカート)からスラックスに変わっても、一般のミャンマー人の心の風景は、いまだに昔のままのお坊さまの国、Last buddhistなのだ。
ミャンマーは最近、アジアのLast frontierといわれることが多いが、それは経済の話。現在でも男の子が生まれると、お坊さまにすることが親の最大の喜びだという。ミャンマーの仏教徒は少なくとも一生に1度は必ず出家する。企業経営者ですら剃髪して修行する。身につけるのはロンジー(巻きスカート)からスラックスに変わっても、一般のミャンマー人の心の風景は、いまだに昔のままのお坊さまの国、Last buddhistなのだ。
◆ 素顔2.最も長い内戦の国
11月の初旬、わが社の向かいにある芝公園でミャンマー少数民族の祭りがあった。初のミャンマー訪問を控えていた筆者は、昼食後の散歩がてらにちょっとのぞいてみた。女性はほぼ全員が鮮やかな刺繍をあしらった巻きスカートに赤い帽子とおそろいで、中国とミャンマーの国境付近に住む山岳民族、カチン族の正装らしい。黒いセータのうえから身につけた銀色に輝く大きな鈴状の工芸品はネックレスだろうか、きらきらと秋の陽に映える。日本人そっくりな顔立ちで、日本語も流暢だ。しかし、カメラを向けると子供たちはあわてて顔を隠す。かなりシャイなようだ。それにしても老若男女、こんなに日本にいたのかと思うほどの人出で、のどかなお祭りだった。
 数日後、この写真をヤンゴンの通訳の女性に見せると、カチン族の祭りはヤンゴンではなかなか見ることができないと羨ましがった。そんなものかとその場は特に不思議にも思わなかったのだが、あとで調べると、カチン族は民族自立をめざしてミャンマー政府と激しい内戦を続けていたのだ。手元のスナップ写真をよく見ると、男の子が手にする小旗はミャンマー国旗ではなく、カチン族の旗のようだ。この子も、ひそかに民族の英雄をめざしているのかもしれない。
数日後、この写真をヤンゴンの通訳の女性に見せると、カチン族の祭りはヤンゴンではなかなか見ることができないと羨ましがった。そんなものかとその場は特に不思議にも思わなかったのだが、あとで調べると、カチン族は民族自立をめざしてミャンマー政府と激しい内戦を続けていたのだ。手元のスナップ写真をよく見ると、男の子が手にする小旗はミャンマー国旗ではなく、カチン族の旗のようだ。この子も、ひそかに民族の英雄をめざしているのかもしれない。
ミャンマーには複雑な歴史があって、100以上もある少数民族の帰属問題は、同国の内政上の最大の悩みといっていい。
19世紀半ば、長い抗争の末にミャンマー族の王朝を滅ぼし、この地を領有したイギリスは、大多数を占めるミャンマー族を支配するために、カレン族をはじめ多くの少数民族を軍・治安要員として教化・組織化した。その際に、欧米の宣教師たちが自然信仰の多い少数民族をキリスト教に改宗させた。このため、カレン族の一部やカチン族のほとんどはキリスト教徒となった。
世にいう大英帝国の分割統治である。しかし、この統治方式は、1948年にミャンマーが独立を果たすと、その後の長い内戦の原因の1つとなった。圧倒的多数派のミャンマー族と少数民族の立場は完全に逆転し、広大な山岳地帯は内戦の巣と化した。民族対立に宗教対立、中国からは国民党の残党やら共産党の工作員、タイやラオスからもヒスイやヘロインを求める商人たちが険しい山を越えてやってくる。何でもありの無法地帯は、やがて「黄金の三角形」と呼ばれるようになる。魑魅魍魎(ちみもうりょう)の横行する文字通りの魔境が誕生した。
1988年、全国的な民主化運動の後に今日に至る軍事政権が誕生すると、いささか事情は変わった。有名なアウンサンスーチー氏の軟禁事件が起き、欧米の政治的、経済的な制裁が20年近く続く(一部は今も続いている)。
この間隙をぬって急速に権益を拡大したのが中国だ。軍事政権を手なずけた中国は、いつしか経済権益をミャンマー全土に広げただけでなく、美しい都マンダレーはいまや中国人租界といわれるまでになった。国民の中国への反感が高まってきただけでなく、資源開発や水力発電事業をめぐって、カチン族など中緬国境の山岳地に住む少数民族蜂起の新たな火種となり始めた。
欧米も、事態の深刻さにようやく気がついた。ミャンマーに圧力を加えれば加えるほど、中国の南進が進む構図を見過ごすわけにはいかなくなった。このままではミャンマー権益だけでなく、東南アジア全域が中国の影響下に組み込まれてしまう。
あくまで私見ではあるが、ミャンマーの民主化と経済開放は、ミャンマー中枢部の中国に対する警戒感と欧米指導者たちの権益確保への利害が一致し、阿吽の呼吸の中で一気に進められたと考えている。(一般的には、現政権の基盤が確立して民主化への余裕が出てきたことや経済成長への国民的欲求が非常に高まってきたことなどが、民主化・経済開放の要因とされている)
この国のすさまじい歴史の中で、日本がこれから権益を確保するには、よほどしたたかな対応が必要だろう。5000億円にも上るODAの債務帳消しという大盤振る舞いをした日本は、この夏、大規模な国際入札案件で相次いで落選した。お上品な座敷犬のままでは、おこぼれにしかあずかれないのかもしれない。