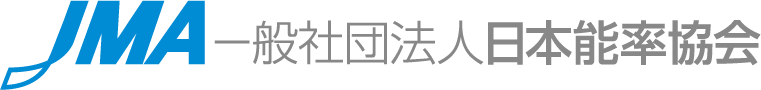シリーズ SDGsを再考する(2) 2019/03/01 コラム Tweet
一般社団法人日本能率協会 KAIKA研究所
田中達郎
◆戦後日本の歩み
貧困や飢餓といった社会課題の克服のために日本ができることは何かを考えたいと思います。そのために戦後の日本が歩んだ歴史を振り返ります。第二次世界大戦の敗戦により、一時的に日本は国としての機能を失いました。ありとあらゆる資源は枯渇し、食べることもままならない困難な時代を迎えます。そこでGHQが主導するかたちで“戦後の”農地改革が行われ、1947年にニューディール政策をもとにした農業協同組合法が、続く1948年には米国の普及制度をコピーした農業改良助長法が制定されます。古くは江戸時代より脈々と続いてきた農業会を改組することで農協(JA)が誕生します。
自給自足の生活が確保され飢餓状態を脱したことで、次に生活改善運動が盛んになります。生活改良普及員の活動は、「考える農民の育成」をスローガンに、“教える”のではなく、自ら気づき、技能を身につけ、工夫することを促しました。かまどや台所、衣食住の改善、家政学などがこうした活動を通じて一般的になっていきます。元来実直で素直な日本人はやがて自らの力で貧困状態を脱しました。
2020年の東京オリンピックを前に日本は湧いていますが、一つ前の東京五輪が開催された1965年は日本の高度経済成長を決定的なものとしました。OECDへの加盟、IMF8条国に移行、東海道新幹線の開通など政策やハードの転換もさることながら、生活面では乳幼児死亡率がアメリカを下回り、生活改善運動における貧困対策という使命も終わりを告げました。当時の華やかな経済成長の背景として、このような社会課題解決の視点が日本の総中流化を支えたのは事実です。
◆経験を活かすことこそ日本の役割

生活改善運動は参加型農村開発の原点となりました。国際開発の現場では営農技術の普及と生活改善運動をセットにした途上国支援が一般的です。欧米とは異なり、日本は貧困を脱する実体験を通じて得た気づきや知識を持っています。ここに日本の社会課題解決における存在価値があると言えます。
遡ること10年前の2009年、BOPビジネスが注目を集めました。途上国を中心に世界に約40億人、5兆ドル規模とも想定される将来市場をマーケットとして捉えた地域の社会課題を解決するアプローチで、有名なところではノーベル賞を受賞したムハマド・ユヌス氏のマイクロファイナンスがあります。一例として、「グラミン・ダノン」はグラミンレディーによるヨーグルト販売(栄養改善・女性の活躍)とマイクロファイナンスによる乳牛飼育支援(収入向上)で、社会課題の克服と持続可能なビジネスを実現しました。従来はWHOの活動と認識されていた分野に企業がビジネスとして取組む画期的な動きです。その意味でBOPビジネスはSDGsビジネスの一部とも言えます。
しかしながら、誠に残念なことに日本におけるBOPビジネスは目立った実績を残していません。他にも、たとえばフェアトレードの市場規模についても、日本の一人あたりの消費額はイギリスのわずか1/150でしかありません。日本人の性質や文化に至る奥の深い要因はありますが、日本人だからこそ出来ること、すべきことがあるはずです。SDGsという世界的な潮流の中で、今こそその役割を担う時が来ています。
◆私たちこそ取り組むべきSDGs
繰り返しになりますが、SDGsが国際目標としてスタートし3年が過ぎました。2030年のゴールまであと12年あります。日本でも着実にその認識が浸透してきており、規模に関係なく企業の取組みが広がりつつあります。冒頭でも触れたように、自治体や学校教育でも積極的に活用されている中で、JMAが北海道で展開している事業においても、SDGsの達成に向けた取組みを通じて地域活性化を実現する持続的な発展を目指しています。
確かに、ブームが起こると一方でネガティブな捉え方をされることもあります。“SDGsウォッシュ”や“補助金目当て”など、心無い人からの冷たい批判にさらされる可能性もあるでしょう。だからやらない、触れないでは、日本は世界からもっと冷たい視線を浴びることになります。そうならないためにも、まずはしっかり本質的なSDGsの理解を深めることで、小さなことでも何かできることを探してみましょう。17個もゴールがあるのですから。ひとつくらい。(完)